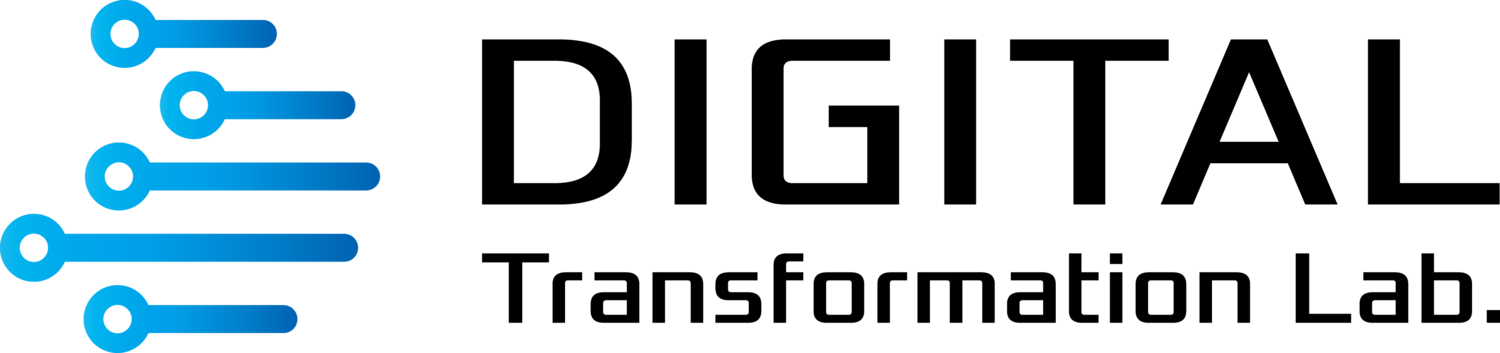円卓コンフィデンシャル(テレ東地上波、テレ東BIZ)対談を通じて学んだDX事例
2025年5月3日に放送されたテレビ東京「円卓コンフィデンシャル」に、企業のDXについて、DX専門家として出演させていただきました。
番組では、マルハニチロ様、LIXIL様、アシックス様といった各社のDXの最前線をご紹介いただき。現在進行中のDXの現場についてお伺いすることができました。
以下に内容の一部を整理させていただきます。
生成AIに関する取組み
今回の円卓会議では、いま大注目の生成AIの活用がテーマに挙がり、各社から利用状況などを伺うことができました。
マルハニチロ様では食品表示などミスの許されない神経を使う業務において、社内ノウハウを生成AIにより共有知化する取組みが進んでいるというお話を伺いました。社内の共有知を現場で活用するためには、新しい仕組みを業務にいかに実装するかが重要となりますが、マルハニチロ様の事例では、高い効果の見込める業務から取り組むことにより、早く成果を実現するアプローチが効果を発揮していると感じました。
LIXIL様のコールセンターでは、コールセンター全体の対応品質を高め、得られたデータを活用したさらなる改善を図る取組みについてを伺いました。経験の浅いスタッフを効果的に支援できる一方、優秀なベテランスタッフの対応品質を高めることは容易ではないというお話でした。このあたりは、今後、データに基づき、課題やお客様の感情を分析できるようになることにより、伸びしろのある領域かもしれません。
アシックス様では、画像生成コンテストを開催し、多くの社員が生成AIにより親しみを持てるよう工夫されている他、参加者の皆様が、AIに何が出来て何が出来ないのかを学ぶ機会になったことが大きな価値とおっしゃっていました。現場の皆さまが、自身の業務にどのようにデジタルテクノロジーを使えるかを自ら考えるようになることは大きな価値があると思います。
生成AIは加速度的に進化が早まっているだけに、いますぐ業務にフル活用できなかったとしても、まずは、できることから取り組んでみるという挑戦が重要だと思います。それにより、
暗黙知を共有知にして、一元的に管理するという新しい業務スタイルを構想可能にする
データを分析し改善しつづけるデータドリブンな業務スタイルに取り組める
現場が新しいテクノロジーを活用し変化を楽しめる組織文化にする
などのDX観点で必要な要素を組織に取り込むことが可能となります。
データドリブンへの進化
DXにおいては、データを獲得し分析し判断することにより、高速に改善を続ける仕組み「データドリブン」が競争の重要な要素になります。そのあたりも各社からお話を伺うことができました。
マルハニチロ様は、データを入力することに抵抗を示す人に対して、データが正しく得られて、循環できる仕組みになれば、どのようなメリットがあるのかをしっかり説明することが重要と話されていました。データを蓄積することが目的となってしまうプロジェクトが世の中には多いのですが、しっかり目的について共通認識にすることは重要ですね。
LIXIL様は、顧客体験の向上をDXの重要な目標に置かれていて、NPS(Net Promoter
Score)という指標(KPI)で定点観測されているとのことでした。共通の指標(KPI)を業務横断的に見える化し、同じ「ものさし」で施策の効果などをレビューできることは、データドリブン組織になるために必要不可欠ですね。
アシックス様は、ランニング管理、記録管理、目標管理サポートなど、消費者の個人データを預かり、消費者に最適なサービスを提供することにより、消費体験向上を図る取り組みをされていました。データドリブンで顧客体験をパーソナライズすることは、顧客への提供価値を高めるための究極の手段でもあります。特に消費者とダイレクトにコミュニケーション可能な業態においては、今すぐ取り組むべき分野と言えます。
データドリブンという言葉はよく聞くけど、何から始めればよいかわからないという声をよく聞きます。上記3社の取り組みも参考にしながら、何のためにどのようなデータを自社で蓄積するべきなのか、それにより、どのように事業判断、経営判断を変えていくことができそうかを社内で協議し、共通認識を持つことも重要です。
組織行動の変革に関する取組み
各社は、単なるデジタル技術の導入で終わらないトランスフォーメーション(組織行動の変革)を目指しており、これらの取組みや課題についてもお話を伺うことができました。
マルハニチロ様では、守りのDXにより、社員の考える時間を創出して攻めのDXへシフトするという方針が示されていました。守りのDXだけになると、様々な組織内の軋轢が増えやすいため、このように先にある攻めのDXが最終目的であると示すことは、DXを停滞させないためにも重要だと思います。
LIXIL様では、ノーコード開発ツールを現場に浸透させる際、まず役員が使う手本を示したとのことです。役員の皆さまがツールを使ってみるということには、大きな抵抗があったかもしれませんが、組織全体に本気で浸透させるためには、もっとも有効な施策となります。組織が本気で取り組むテーマについては、組織の本気度を見せることが重要です。
アシックス様のIT部門は、抵抗を感じ、現状維持しようとする社員の姿勢を変えるため、道具を与えて終わりではなく、使ってもらうための工夫と粘り強さを重視されていました。DXにおいては、デジタルと人の業務をいかに融合できるかが重要であり、そのためには、人の気持ちを理解することがトランスフォーメーション(変革)成功の第一歩です。そのために地道な努力が必要であることを改めて教えていただきました。
私からは、各社の先進的な取り組みに対して、DXの本質や組織変革の重要性について解説させていただきました。DXの本質は、単なるデジタル化ではなく「提供価値の再設計」、そしてゴールは、市場の変化に合わせて「変化し続けられる組織になること」です。
DXは一朝一夕には達成できません。まずは小さな成功体験を積み重ね、組織全体で変化を楽しめる文化を醸成することが重要です。
詳細については、テレ東BIZで配信されているアーカイブ(放送版、配信版)をぜひご覧ください!
当日の収録の様子